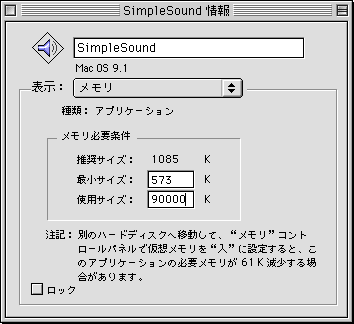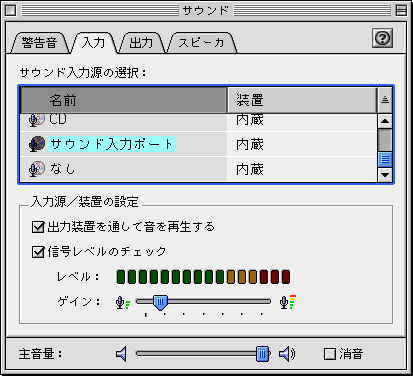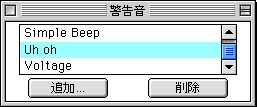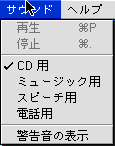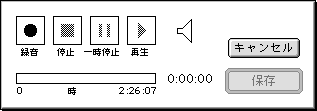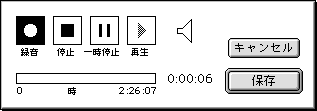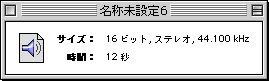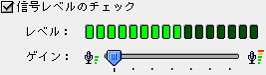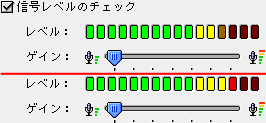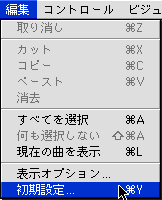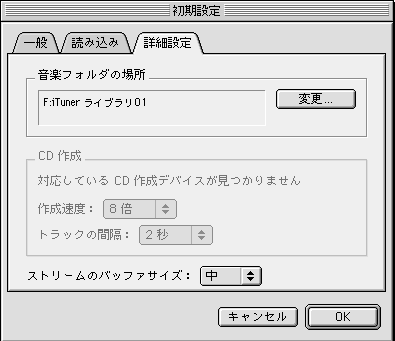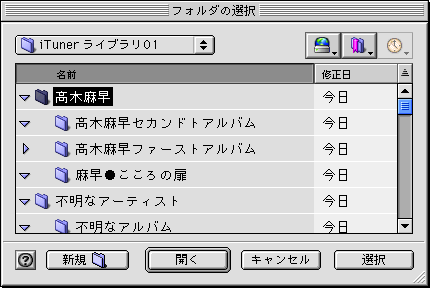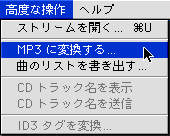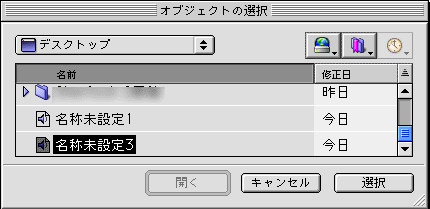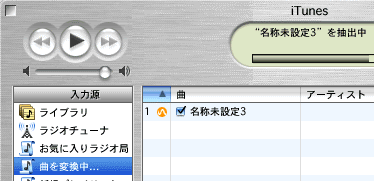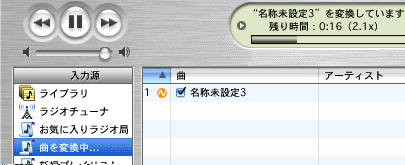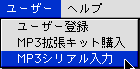|
||||||||
丂 |
||||||||
丂 |
||||||||
|
|
||||||||
|
傑偨丄MP3僼傽僀儖壔偝傟偨丄僼傽僀儖偺曐懚偝傟偰偄傞応強偑丄iTuner 儔僀僽儔儕01僼僅儖僟亜晄柧側傾乕僥傿僗僩僼僅儖僟亜晄柧側傾儖僶儉僼僅儖僟偺拞偵丄曐懚偝傟偰偄傞偺偱丄杮棃丄曐懚偟偨偄応強偵丄MP3僼傽僀儖傪堏摦偝偣偰偔偩偝偄丅 嵞惗價僢僩儗乕僩乮乣kbps偲昞帵偝傟偰偄傞偲偙傠乯傪丄崅偔愝掕偟偰偄傞偲丄MP3僾儗乕儎乕乮CD-R/RW僞僀僾傕娷傓乯帺懱枹懳墳偱丄嵞惗晄壜擻偵棊偪擖傞応崌傕偁傝傑偡偺偱丄偍庤帩偪偺MP3僾儗乕儎乕傗丄偙傟偐傜MP3僾儗乕儎乕傪丄峸擖梊掕偺曽偼丄MP3僾儗乕儎乕偺懳墳嵞惗價僢僩儗乕僩偵丄拲堄偝傟偰偔偩偝偄丅亙2001.11.20 捛壛亜 iTuner偺愢柧偲廳側傞晹暘傗丄愢柧夋憸偑懡悢偁傞偺偱偡偑丄婎杮揑側嶌嬈偵巟忈傪梌偊傞傕偺偱柍偄堊丄崱夞偼丄妱垽偟傑偟偨丅 偁乣乣丄旀傟傑偟偨偑丄傗偭傁傝丄愄偺嬋偼丄僀僀乣乣傢両 偱偡偺偱丄摉暘偺娫偼丄峏怴嶌嬈偼丄偍媥傒偟傑乣乣偡丅 MP3僼傽僀儖壔偝偣偨LP儗僐乕僪偼丄1970擭戙弶摢偐傜80擭戙弶摢傑偱偺儗僐乕僪偱丄堜忋梲悈丄偁偺偹偺偹僼傽乕僗僩儔僀僽丄僆乕儖僫僀僩僯僢億儞VIVA孖栄乮巺嫃屲榊丄傾儞僐僂丄傾儅偪傖傫丄僥偭偪傖傫丄僇儊偪傖傫偭偰尵偭偰傕30嵥戙偵偼敾傫偹乣偩傠偆側丠両乯丄僒僀儌儞偲僈亅僼傽儞僋儖丄壀嶈桭婭丄崅愇桭栫偲僓丒僫僞亅僔儍乕僙僽儞仌彧乆嶳僐儞僒乕僩乫78丄崅栘杻憗丄嶳揷僷儞僟丄愹扟偟偘傞傑偱丄庢崬傒偑廔傝傑偟偨偑丄偙傟傜埲忋偺検偺丄傾儕僗乮僠儞儁僀仌傋乕傗傫仌僉儞偪傖傫乯偺儗僐乕僪偲丄EP斦偑巆偭偰偍傝丄偦偺忋丄僥乕僾偵娭偟偰偼丄傑偭偨偔丄庤傪晅偗偰偄側偄忬懺偱偡丅 丂 |
||||||||
|
丂
丂 丂
丂 |
||||||||
|
丂
丂 |
||||||||
|
亙儗僐乕僪恓斕攧亜 COMMUNET--斈梡儗僐乕僪恓偱桳柤側丄姅幃夛幮僫僈僆僇僩儗乕僨傿儞僌惢昳傪庢傝埖偆斕攧揦偱偡丅 亙Mac懳墳USB愙懕僆乕僨傿僆擖弌椡傾儞僾亜 亙MP3娭楢儂乕儉儁乕僕亜 |
||||||||
| 丂 | ||||||||
| 丂 | ||||||||
|
丂 |